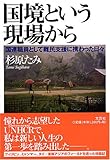猫が見ていた
2018年5月18日 読書記録第6紀(13.08~)猫を飼うふりを続けていた男の謎。同じマンションの住人の猫を密かに飼う女…現代を代表する人気作家たちが猫への愛をこめて書き下ろす猫の小説、全7編。猫好き必読です。
巻末には「猫小説オールタイム・ベスト」紹介も。
【収録作品】
「マロンの話」湊かなえ
「エア・キャット」有栖川有栖
「泣く猫」柚月裕子
「『100万回生きたねこ』は絶望の書か」北村薫
「凶暴な気分」井上荒野
「黒い白猫」東山彰良
「三べんまわってニャンと鳴く」加納朋子
「猫と本を巡る旅 オールタイム猫小説傑作選」澤田瞳子
https://www.amazon.co.jp/dp/4167908905/
作者名を見て勝手に猫ミステリーアンソロジーだと思い込んでいましたが、だいぶ広義のミステリー、かなぁ、という感じの短編集でした。
ラノベ作家による短編集よりは、さすがの一般向け小説の人気作家を集めているだけあって、どれもそつなく仕上げてきている印象。
でも、こちらも文芸誌の特集に合わせて原稿を集めたものらしく、この1本、と思える(私にとっての)佳作はなかった。(失礼)
冒頭の湊かなえ以外は”猫が人間語を話さない”、私にとっての猫小説試金石をクリアしているにも関わらず、である。つまり、猫視点でない猫小説(短編)はいかに書くのが難しいか、ということだろうと思う。
(ちなみに、湊かなえの作品も猫目線とはいえ、自分の親猫が野良から家ネコになるまでを語っている語り手であるので、人間語を話していることがあまり気にならない)
有栖川有栖は、自分のシリーズ作品の1作品、という位置づけで書いていて、上手いやり方だなぁと思った。短い原稿の中で、既存の設定を使うことで世界観やキャラクターの説明を省いている。
そつなく書かれている、という印象はいっぽうで”猫愛あふれすぎ(独立した小説としてはいかがなものか)”な作品はあまり多くなかったと思う。
その中で、湊かなえは、おそらく作家自身を客観視して作品にしているエッセー風でもあって、自分の飼っている猫の話かしら?と思わせる。
加納朋子は、猫が出てくるソーシャルゲームをきっかけに親との関係を見直す話で、生身の猫は一瞬しか出てこないけれど、ゲーム内の猫の描写から、猫が好きなんだろうと思わせる。
北村薫は、以前新聞のエッセーで飼い猫のことを書いていたかインタビューを受けていたか、猫好きだったと記憶しているけれど、この短編は「吾輩は猫である」をきっかけにした人の心の描写だったので、あまり猫愛は感じられなかった。
あまり「猫大好き~」だけの話も好きではないけれど、猫が風景にとどまっているものも、猫をテーマにしたアンソロジーとしては物足りない。むー。
コメントをみる | 

猫だまりの日々 猫小説アンソロジー
2018年5月11日 読書記録第6紀(13.08~)YA(BL含む)女性作家5人による、猫をテーマにしたアンソロジー。
かなり力量に差が出たなぁというのが読後の印象。
猫をテーマにすると、どうしても猫に人間語を話させないと話が進まないし、そうするとある種のファンタジーとしてしか成立しない。短編の中でファンタジーの法則を読者に理解させ、さらにオチをつけるのは相当の力技が必要なのかもしれない。
(この後、猫ミステリアンソロジーと猫SFアンソロジーを読む予定で、それらを読むとこの認識は変化するかもしれない。)
そんな中で、技あり、と思ったのは谷瑞恵と一穂ミチ。実はどちらも初めて読む作家さんでしたが、谷瑞恵は●●ミステリ(これを言うとネタバレになるので伏せ字)であり、かつ主人公が過去を乗り越える成長も描いており傑作。
一穂ミチも、不慮の事故で亡くなった主人公の男性が猫に転生して残された妻に拾われる、という物語でありながら実はミステリ要素もあり、しかもネットのネコ好きコミュニティで流布している都市伝説「猫は一生に一度だけ人間語を話す」(これは「NNNからの使者」のNNN(都市伝説というよりネットジョーク)とは違い、どちらかといえば伝説に近い)を上手く使っており、座布団10枚もの。
上記2作の冴えには一歩譲るけれど、さすがの真堂樹もネタはありがちながらきちんと作品として成立させていた。
残りの2作はあいにく私の好みではなかったけれど、短編は、いいネタを思いつくかどうかが勝負であり、今回のようにテーマが初めに決められていて締切までに書き上げなければいけない場合、ネタが降りてこないとツラい、というのはあるだろうし、下手に猫が好きだとそこに引きずられてしまって短編小説としてのおもしろさを深掘りしきれない、ということはあるのだろうなぁと思いました。
とくに椹野道流は、長編で読みたい世界観でした。
仕事を失くした青年と、そんな青年の願いを叶えるべく彼のもとを訪れてきた猫との心温まる交流(椹野道流「ハケン飯友」)
かつて飼っていた猫に会えるというウワサがある、ちょっと不思議なホテルにまつわる物語(谷瑞恵「白い花のホテル」)
猫飼い放題をうたう町で出会った、猫があまり得意じゃない彼女と彼のせつない恋(真堂樹「猫町クロニクル」)
猫が集まる縁結びの神社で起きた、恋と友情をめぐるアレコレ(梨沙「縁切りにゃんこの縁結び」)
後に猫へと生まれ変わり、妻に飼われることになった男の生活(一穂ミチ「神さまはそない優しない」)
オレンジ文庫の人気作家陣が描く、どこかにあるかもしれない猫と誰かの日々。
全五編を収録。
https://www.amazon.co.jp/dp/4086801671/
かなり力量に差が出たなぁというのが読後の印象。
猫をテーマにすると、どうしても猫に人間語を話させないと話が進まないし、そうするとある種のファンタジーとしてしか成立しない。短編の中でファンタジーの法則を読者に理解させ、さらにオチをつけるのは相当の力技が必要なのかもしれない。
(この後、猫ミステリアンソロジーと猫SFアンソロジーを読む予定で、それらを読むとこの認識は変化するかもしれない。)
そんな中で、技あり、と思ったのは谷瑞恵と一穂ミチ。実はどちらも初めて読む作家さんでしたが、谷瑞恵は●●ミステリ(これを言うとネタバレになるので伏せ字)であり、かつ主人公が過去を乗り越える成長も描いており傑作。
一穂ミチも、不慮の事故で亡くなった主人公の男性が猫に転生して残された妻に拾われる、という物語でありながら実はミステリ要素もあり、しかもネットのネコ好きコミュニティで流布している都市伝説「猫は一生に一度だけ人間語を話す」(これは「NNNからの使者」のNNN(都市伝説というよりネットジョーク)とは違い、どちらかといえば伝説に近い)を上手く使っており、座布団10枚もの。
上記2作の冴えには一歩譲るけれど、さすがの真堂樹もネタはありがちながらきちんと作品として成立させていた。
残りの2作はあいにく私の好みではなかったけれど、短編は、いいネタを思いつくかどうかが勝負であり、今回のようにテーマが初めに決められていて締切までに書き上げなければいけない場合、ネタが降りてこないとツラい、というのはあるだろうし、下手に猫が好きだとそこに引きずられてしまって短編小説としてのおもしろさを深掘りしきれない、ということはあるのだろうなぁと思いました。
とくに椹野道流は、長編で読みたい世界観でした。
後藤 太輔 (著),現代書館,2018.04
フィギュアスケート界では男女選手の交流・協力活動が多く、引退後も、コーチ、プロスケーター、振付師、衣装デザイナーなど多ジャンルで活躍している。インストラクター協会理事にも女性が多く、他のスポーツと比べ、ジェンダーバイアスが少ない競技といえる。海外では、現役選手による同性愛カミングアウト、アラブの選手によるヒジャブ着用など、社会に対して積極的にアピールする選手も多い。本書は、フィギュアスケートとジェンダーを切り口に、スポーツと社会の繫がり、2020年東京五輪パラリンピックへの向き合い方を伝える。 現役記者ならではの豊富な取材に基づく逸話が満載!
「中国と日本が政治的に緊張しても、スケート界の関係は良好です」
「日本は、スポーツがなくても幸せな国だったんだな」
「私は美しさで勝負する。それが自分だから。銀盤では私は女だと思って滑っているんです」
朝日新聞現役記者がつむぐ、スポーツと平和を愛する人から生まれる言葉たち。
1章 フィギュアスケートとジェンダー
2章 スポーツから始まる友好
3章 ぼくらに寄り添うスポーツの力
4章 社会を変えるスポーツの力
https://www.amazon.co.jp/dp/4768458319
読了後、編集者と著者のこんなやり取りが思い浮かんだ。
編「タイトル『ぼくらに寄り添うスポーツの力』? うーん、いまいち訴求力がないんですよね……。ちょうど羽生が金メダルを取ったばかりだし、第1章のタイトルを本全体のタイトルにしましょう!」
著「え……。でも、フィギュアスケートの話は全体の3分の1くらいしかありませんよ。それに、僕がこの本で訴えたいのはスポーツが社会をよくする力を持っている、ということであって……」
編「でも、ぶっちゃけこのタイトルでは売れませんよ。売れなきゃ、あなたの主張が誰にも届かない、ということです」
著「……」
編「わかりました! では元のタイトルを副題にしましょう。それで手を打ちましょうよ!」
と、いうわけで、タイトルは全体の4分の1もない第1章だけの内容であって、その後もぽつぽつとフィギュアスケートの話も出てくるものの、全体のほぼ半分はアメリカのアメフトや野球選手の社会貢献活動について紹介する内容。それはそれで興味深く読んだし、著者は朝日新聞記者としてツイッターでフィギュアスケート関連のツイートもしていて、知識もあって信頼性の高いネット記事なども執筆しているので、たとえタイトルどおりの内容でなくても許せる。
ええ、たとえ期待どおりの内容ではなかったとしても(怒)。
もっとも興味深かったのは、日本におけるフィギュアスケートの歴史を簡単になぞっている部分でした。
小塚祖父が太平洋戦争中に満州でフィギュアスケートに触れ、帰国してから名古屋で広めて、ロシア語もできたことからフィギュア大国だった旧ソ連とのコネクションを作って名古屋のフィギュアが強くなっていった話は知っていましたが、都築先生が松戸にあったリンクでやはり旧ソ連とのつながりを築いていたことと、日本人で最初にクリケットに行ったスケーターだったことなど、新たに知ったことでいろいろ腑に落ちました。
クリケット(というかカナダ)に行く選手はあまり聞かないですが、本田岳史と織田信成がカナダに行っていたのは聞いていて、いろいろな条件があったのでしょうけれど「名古屋以外」の選手がカナダに行ってるのだなぁと思っていて、つまり都築先生ルートだったのかしら、とか。
こういう日本フィギュアスケートの歴史や師弟関係の系譜と海外とのコネクションみたいなの、どこかでまとめられてないかしら。
コメントをみる | 

NNNからの使者 猫だけが知っている
2018年4月20日 読書記録第6紀(13.08~)最近寂しさが身に染みる独身男藤本誓のもとに、やけに模様がくっきりとした三毛猫が現れるようになった。と同時に、会社からの帰り道、野良と思われる白猫が「お腹すいた」と猛アピールしてくるように。食べ物を与えるようになった誓は、次第に猫が飼いたくなり、ペット可物件に入居してしまう(表題作「猫だけが知っている」より)。今日もミケさんたちは、猫好きな誰かのことをじっと見ている!?ページをめくるたび、あなたも猫の魅力のとりこになる、モフモフ猫小説誕生!
https://www.amazon.co.jp/dp/4758441251
Amazonにお薦めされて発行を知ったネコ小説。
著者の矢崎在美といえば人語を話し普通に人間社会で生活するピンクのぬいぐるみが主人公の「ぶたぶた」が有名で、私もシリーズ当初は欠かさず読んでいたのに、最近こんな猫小説に手を出していたとは不覚にもチェックしておりませんでした。
というわけでさっそく入手。
タイトルに入っているNNNとは、著者はあとがきで都市伝説、と言っていますが、より正確にはインターネットの猫好きコミュニティにおける有名なネットジョーク。はからずも捨て猫や野良猫を浩って飼い始めることを「NNN(ねこねこネットワーク)という秘密結社から猫が派遣されてきた」と言い慣わしていて、そこから様々なNNNの設定が作り上げられています。
この本は、NNNから猫が派遣される、つまり様々な立場の人が家のない猫と出会い、飼い始めることになる短編小説集で、拾う立場の人間と、ネットワーク側の野良猫の視点から語られています。
どの話も必ず最後は野良猫が飼い主と出会う話なのでハッピーエンドが保証されている点で、安心して読めますが、だからこそ、それをフィクションとして成立させるにはもうひと捻りほしかったところですが、気楽に読める本ではあります。
今月になって続編も刊行されたので、また読んでみます。
警視庁生きものがかり
2018年4月1日 読書記録第6紀(13.08~) コメント (2)警視庁生活安全部生活環境課環境第三係――絶滅のおそれのある動植物の密輸・売買事件の捜査をする、この係を人はこう呼ぶ――「警視庁の生きものがかり」!
警視庁にそんな部署あったのか!?
はい、本当にあるんです!
「カメもサルもワニもレッサーパンダだってオレが守る!」
「動物愛」なら誰にも負けない、この男が本物の
「警視庁の生きものがかり」!
「愛」あればこそ、仕事に燃える「生きものがかり」の大活躍を描く、
笑いあり、怒りあり、涙もちょっぴりありの感動必至のノンフィクション!
https://www.amazon.co.jp/dp/4062206838/
昨年夏に放送されたテレビドラマ「警視庁いきもの係」の原作はこちら(http://yogiribook.diarynote.jp/201708240027056166/)。
放送直前に、実際に警視庁で生きものに関する事案を扱う部署を立ち上げた方の手記が出版されました。
すぐに買ったものの手に取るのが後回しになってこんなタイミングに(汗)。
ドラマとの違いは、ドラマ(というか原作のミステリ)が扱うのが、ペットの動物を引き金に起こる殺人事件なのに対し、現実の「生きもの係」が扱うのは主にワシントン条約違反の希少動物の密輸事件であること。
ミステリにするにはやはり人が死なないと緊迫感はないし、被害者が死なないと犯人がすぐに分かってしまうから仕方がない。
でもやっぱり現実にそんな殺人事件がおこるわけではなくて、やはり密輸事件が一番多いのでしょうね。
事件に気づくところから、捜査の過程、逮捕に至るまで、どう考えてどう追い詰めていったかが丁寧に描写されていて、警察用語も解説付きで出てきてとても面白かった。検察にはねられず、裁判で有罪が取れるようにどうやって証拠を固めるか、といったあたり興味深かったです。
いっぽう、この話は警察に限らず、新しいビジネスを立ち上げる事例としても面白く読めました。
例えば、著者が警察官になったすぐの頃、上司から
「十八番をつくれ!」
と言われたという話、私も新人のころに先輩に言われたものなぁ。著者はもともと動物が好きで、趣味で魚や爬虫類を飼っていて、たまたま覗いた熱帯魚店で展示・販売が禁止されている生物を見つけたことがきっかけで立件し、これが自分の得意分野だ、と思い定めて
庁内で生きもの事案を1件扱うとそういう事案はその人に集まってくるし、そのことでからかわれたりもしたらしいけれど、続けることで専門家として1部署立ち上げることに繋がった、なんて、どこの会社でもどんな(オタク)社員でも参考になるはず。
他にも、外部の専門家とのパイプを作るところとか、情報はたくさん出すとそれだけ集まるところとか、自分が仕事でやってきたことと通じる部分がたくさんあって、ビジネス書としても強く推したい。
文章は、拙いわりに読みやすく、文章を書くのがたまたま上手い人だったのか、ゴーストライターが入っているのか考えながら読みましたが、あとがきに「約1年にわたり取材していただいた●●さん」と謝辞があったので、やっぱりライターが入っているらしい。こうも自然に「普段あまり文章を書きなれていない感じ」にまとめられるなんて、けっこうライターさんの力量にも感心しました(笑)。
希少動物の生態などもイラスト付きで紹介されていて、1冊で3度おいしいおススメの本です。
フィギュアスケート界で人気実力ともにナンバーワンを誇る羽生結弦。しかし羽生のスケーティングを語るとき、たいていの人は「美しい」「観客を引き込む」という曖昧な表現に終始するか、「何回ジャンプを跳べたか」という点をクローズアップするばかりだ。著者は、38年間この競技を見続けてきた生粋のスケートファン。マニアックな視点で、「羽生の演技の何がどう素晴らしいか」を、表現、技術の両面から徹底的に分析する。羽生以外の現役男子・女子スケーターはもちろん、歴代スケーターたちの名プログラムもフィギュア愛炸裂で語りつくす!
猫は、うれしかったことしか覚えていない
2018年2月7日 読書記録第6紀(13.08~)ありがとう、猫たち。
今を生きることを教えてくれて。
「センパイコウハイ」シリーズのエッセイストと、『ねこまみれ帳』の画家による、くすっと笑えて、しみじみ沁みる、猫のはなし。
【「猫は、うれしかったことしか覚えていない」獣医師から聞いたその言葉は、以後、私の中に生き続けています。猫は、過ぎたことを引きずることなく、うれしかったことだけを積み上げて生きていくのです。(表題エッセイより)】
「センパイコウハイ」シリーズのエッセイスト・石黒由紀子と、『ねこまみれ帳』の画家・ミロコマチコが、文と絵で綴る、可愛くて、くすっと笑えて、しみじみ沁みる、「猫のはなし」。
「猫は、好きをおさえない」「猫は、まっすぐに表す」「猫は、落ち込まない」「猫は、誰かとくらべない」「猫は、考える前に動く」「猫は、命いっぱい生きている」……など、猫が教えてくれる、幸せのコツ。
死線の向こうに (集英社文庫)
2018年2月5日 読書記録第6紀(13.08~)従軍取材で疲弊しきったドーソン・スコット。名付け親ゲイリーの依頼で、40年間姿をくらましている過激派ウィンガートを探すため、彼の息子と思われる男、ジェレミーを追う。ドーソンはジェレミーの元妻アメリアに接近、彼女とその息子たちに惹かれるも、心に傷を負うドーソンには立ちはだかるものが多すぎた。そんななか、身辺に起きた不可解な出来事は、殺人事件に発展し…。サスペンスの女王の真骨頂!
先日ひさびさに読んだサンドラ・ブラウンが面白かったので、ちょっと古い(邦訳2014年刊)こちらを手に取ってみました。
ロマンス小説なので基本は善男善女が出会って恋に落ちて障害を乗り越えてハッピーエンドという大筋は変わらないはずで、出会うきっかけや乗り越える障害しか物語のバリエーションがつけられない。ゆえに、長く多作な作家ほど、このバリエーション部分が複雑になっていくのは仕方がないとして、上のあらすじではどんな話なのだか見当がつかず、サンドラ作でなければ手に取らなかっただろうと思います。
実際読んでみて、短い文字数にまとめるなら上のあらすじは過不足ない情報が詰め込まれているのですが、それだけ設定が複雑な話であり、逆にロマンス部分に入り込みづらいというジレンマを抱える結果になってしまったのかしら、と、読み終わってから思います。
というのも、実は最後にかなり意外などんでん返しがあり、それこそがヒーローがヒロインとの恋愛に躊躇する理由でありロマンスの障害であるのですが、読者には伏せられているために「なんでこの男はここまでウジウジ思い悩んでるんだ!」とフラストレーションがたまるのです……。
いちおう、真の理由を隠すため「男は従軍取材で疲弊した(PTSD発症)」という設定もかぶせてあるのですが、PTSDになるに至った従軍中のショッキングな事件の詳細すら最後まで引っ張られているものだから、読者としてはなかなかヒーローに感情移入できず、読み進めるスピードが上がりませんでした。
が。そんな煮え切らなさも最後のどんでん返しまで。
そこまでくれば後は一気読みでした。隠されていた謎が次々明らかにされてカタルシス。そして、読了してから振り返れば、
「いくらサンドラでも、そんなネタで書こうとしたら、そりゃこうなるしかないよね」
という、上のような感想となるのでした。
さらに、この複雑な設定を成立させるためにあちこちでかなり強引なご都合主義を繰り出していて、そこも物語に入り込めない一因だったかと。
いくら腹をすかせた闘犬3頭でも、大の大人2人を跡形もなく食い尽くすことは無理だろう……。(それで死んだと見せかけて実は生きていたネタ。話の早い段階で明らかになるのでネタバレには含まれないと判断)
ま、ロマンス小説作家は多作なので、たまにはこういうこともあるよね。
コメントをみる | 

壊された夜に (集英社文庫)
2017年12月31日 読書記録第6紀(13.08~)場末の酒場で射殺事件発生。現場から、顔に傷のある男と地元の会社経営者ジョーディが姿をくらました。捜査の結果、死んだ男は殺し屋だったことが判明。警察は、現場から消えた二人の行方を追う。一方、ジョーディは、顔に傷のある男に拘束され、緊迫の夜を過ごしていた。正体不明のこの男の目的は何なのか?ついに、決死の行動に出たジョーディだったが…。どんでん返し連発サスペンス!
一時期熱心に読んでいたサンドラ・ブラウンですが、発行元が新潮社から集英社に移ったころからなんとなく遠ざかっていました。
先日、以前から気になっていたコニー・ウィリス「ドゥームズデイ・ブック」下巻に入ったあたりでどうしても読み進められず挫折して、もうちょっと気楽に読める本を読みたいと、書店で眺めていたら久々に目に留まり、サンドラの新刊を手に取りました。
ちなにに本文560ページで1,200円。文庫本もだんだん値上がりしてくるなぁ。
サンドラ・ブラウンはいわゆるロマンス小説作家で、その中でも”ラブ・サスペンス”の第一人者と言っていいと思います。
ロマンス小説は、美男美女が出会ってから恋をして幸せになる、というフォーマットはとにかく崩せないため、どうやってバリエーションをつけるかで非常に腕を問われるジャンルだと思います。
そういう意味ではBL小説(およびマンガ)も同じ宿命を負っていますが、こちらはまず雑誌掲載ありきで、つまり1話の分量が非常に少なく、とするとほとんど出会ってすぐに恋に落ちてあっという間に体の関係に至らないとならず、ロマンス小説よりさらにハードルが上がります。まあ、それはさておき。
この話では、ヒーローはヒロインの殺害を請け負った殺し屋で、とするとまともに二人が出来上がったところで安定した生活ができるわけではなく、いったい作者はどこへ落とし込むつもりなんだろう、と探り探り読んでいましたが、分厚い本の半ばを過ぎて驚きの展開。
いえ、可能性として考えなくはなかったのですが、そこへ至るまでに読者には「それはちょっと難しい展開では…?」と思わせる描写を盛りだくさんに盛り込んでおいて、手のひらを返してみせる。思わず心の中で「サンドラ~、やられたよ;;;」と嘆きました。
物語の後半は、ヒロインを殺そうとする裏社会の犯罪者と、その犯罪者の不利な情報を持っているヒロインの弟とヒロインを守ろうとするFBIとヒーローの四つ巴の攻防になだれ込むのですが、その中で明かされる犯罪者の正体もなかなか予想外でした。
物語が複雑で、ヒロインもヒーローも大規模詐欺を行った犯罪者とその部下だった弟も嘘をつきまくりで、(冷静に考えると無理のある展開もあるのでしょうが)(少なくとも、潜伏中にいたしちゃうヒーローとヒロインの展開は無理がありすぎるのですが/汗)原題の「STING」そのままの物語でしたね~。とても面白かった! 後半は一気読みでした。
コメントをみる | 

猫がよろこぶインテリア
2017年9月9日 読書記録第6紀(13.08~) コメント (1)
猫4匹と暮らすフォトスタイリスト・ ヤノミサエの 背伸びをしないアイデア集
猫がいると、猫ベッド、猫かご、猫クッションなどが増え、猫のごはん台やトイレで床が占拠され、気がつくと、おしゃれとはほど遠い部屋に……。猫がよろこぶ暮らしも、好きなインテリアもあきらめたくないヤノミサエが考えた“すっきり&シンプル”な暮らし術を大公開!
相変わらず猫本が続々刊行されています。全部買っていてはキリがないので厳選していますが、これは割と自分にヒットでした。
インテリアの好みがシンプルとかシックとか、そういう傾向で自分と近かったことと、猫グッズとインテリアの調和が具体的だったことがよかったかと。
猫と暮らす素敵なおうち紹介本や記事で、自分に合わないなぁと思うのは
(1)カワイイ(←反語)猫モチーフのグッズが並んでいる
(2)おしゃれすぎてトイレや掃除道具などの生活感がない(もしくは紹介されていない)
ような本。これら「カワイイ」と「超金かけてます」を両極端として、その間をとりつつやや(2)寄り、かつ自分の現実(オンナ1人マンション暮らし雑種猫1匹)とかけ離れていないとGood。
その点で、この本の著者は女性の一人暮らしで猫4匹、戸建てとはいえ狭小住宅なので、自分の生活からちょっと背伸びしたら届くかも?というちょうどいいあたりに落ち着いているので、自分にはよかったです。
なので、私と環境が違う人にはピンと来ないかもしれない。
いちおう、巻末に他の猫飼いのお宅もいくつか紹介していて状況の違う人にも目くばせが効いている。
などと思っていたら、たまたまこんなネット記事を見つけた。
「無印良品の家-鎌倉の家大使の住まいレポート」
https://house.muji.com/kamakuranoie/mado170904/
この著者、無印良品の家に住むモニターさんだった!
でも本にはそのことをまったく触れていないし、このブログでは「みーさん」と名乗っていて本のことを触れていない。いいバランス感覚だと思う~。
小鳥を愛した容疑者
2017年8月23日 読書記録第6紀(13.08~)銃撃を受けて負傷した警視庁捜査一課の鬼警部補・須藤友三は、リハビリも兼ねて、容疑者のペットを保護する警視庁総務部総務課“動植物管理係”に配属された。そして、そこでコンビを組むことになったのが、新米巡査の薄圭子。人間よりも動物を愛する薄巡査が、現場に残されたペットから名推理を披露。難事件を解決する!
放送中のドラマ「警視庁いきもの係」の原作第1巻。
原作の方のシリーズ名は「警視庁総務部動植物管理係」でしたが、ドラマ化に合わせたのか今年に入って刊行された第4巻と、2巻以降の文庫版ではシリーズ名が「警視庁いきもの係」とついている。ちなみに第1巻にはまだシリーズ名がついていません。
さらに言うとドラマ化を受けて関連書として企画が通ったのか、現実の警視庁で動植物を担当する部署のOBが執筆した「警視庁生きものがかり」という本が今月刊行され、カオスな様相を示しています。
(原作を読もうと思って検索して混乱した…)
第1巻には短編4本収録。動物のスペシャリストだがやや常識に問題のある探偵役(薄巡査)と、刑事としてはスペシャリストだが動物に関しては素人のワトソン役(須藤警部補)の掛け合いでクスリとさせるライトミステリ。
現実には存在しなかった特殊部署を作ることでフィクション度が高まるのでちょっと無理めな捜査や推理も受け入れられる。まあ、内心ツッコミ入れつつ楽しく読めました。
なお、ドラマ版は多少設定を変えていて、特に原作では捜査一課で須藤のよきライバルだった石松警部補を、ドラマでは須藤の元相棒で須藤を敬愛している15歳下のイケメンに設定したことで萌え度が跳ね上がっているところは、純粋に上手い改変だと思うよ! その手の「腐女子はこういうの好きだよね」系改変には鼻が利いて避けるほうだった私がこうして引っ掛かったのだから!!
原作の須藤と石松の、悪口を言い合うよきライバルって関係もおいしいですが、すると須藤から薄へ育まれる好意が男女のそれっぽく感じられる。それはそれで王道ですが、ドラマ版だと薄役の橋本環奈にまだそういう色がつくのは避けるためか、どちらかというと父が娘に対する好意的に描かれていて、そういうのも長く続けるドラマとしてはよい改変かと思います。とすると余計に、須藤の横にイケメン石松を置くのは(疑似恋愛関係を石松側に向けられるので)よいと思うのです。
……そんな分かりやすいエサには釣られないけどね!(負け惜しみ)
コメントをみる | 

みをつくし料理帖(全10巻)
2017年8月5日 読書記録第6紀(13.08~) コメント (2)料理だけが自分の仕合わせへの道筋と定めた上方生まれの澪。幾多の困難に立ち向かいながらも作り上げる温かな料理と、人々の人情が織りなす、連作時代小説の傑作ここに誕生!
ずいぶん前に読了したものの、記録を書いていなかったので今さらながら書いておきます。
NHKの土曜ドラマで主役を黒木華が演じると聞き興味を持って、ドラマの1,2回程度を見たところで辛抱たまらず原作に手を出してしまい、ほぼ一気に読み通しました。完結してから読み始めてよかった。
主人公は料理の天才なのですが、次から次へと不幸や困難に襲われて、その都度料理の才と、誠実な人柄で味方につけた人の助けで乗り越えていくお話。よくもまあ、作者はこれだけ様々な困難を思いつくものだ、と感心するほどヴァリエーションに富んだ不幸オンパレード。
例えばジャンプマンガだと、主人公の困難は基本的に「より強い敵」で、主に試合形式で対戦相手がどんどん強くなるにつれて主人公も強くなっていき、いつの間にか主人公が人外になってしまうインフレーションを起こしてしまいがちです。
でも、この話では困難にヴァリエーションが大きいので、主人公の料理の腕がどんなに圧倒的でもあまり単調にならずインフレにもならないところが上手いです。
物語の芯となる主人公の目的の一つが明らかになるのはかなり話が進んでからで、それがやや意外に感じました。どれだけ早く主人公の目的を明確にするかが読者を引き込むポイントかと思っていたので。
もう一つの目的である、「自分の主人の潰れた料理屋を再興する」というのは比較的早いうちに明らかになりますが、それは結局この物語の中では成就しないですし。(巻末の付録で、それが成就したことがほのめかされる)
そこは、物語の王道パターンから外す、というかずらしていることが興味深い。
主人公の恋愛部分についても、当初、主人公に惹かれる2人のいい男、という三角関係図式なのに、うまく捻ってある。
つまり、この物語は主人公に3つのタスクを課して、それぞれのタスク(目的)のラインは王道パターンにひねりを利かせておいて、少しずつ山場をずらしながら組み合わせて最後に3つを回収するという大きな構造になっている。
文庫1冊に短編4話を掲載して文庫書下ろし。作者は当然最初から全体を計算していたはずで(文庫後半につくようになったあとがき的なコーナーでも明かしている)、どういう発想でこういう構造を思いつくのか、不思議になる。
この読書記録は、基本的に読了した日付で書いているのですが、このシリーズを読了したのがいつだったか忘れたので、この記事の日付については適当です。7月中には読み終わっていたはずですが、これを書いている9月3日現在、一番古く設定できるのが8月5日なのです……。
国境という現場から―国連職員として難民支援に携わった日々
2017年6月28日 読書記録第6紀(13.08~)憧れから志望したUNHCRで
私は新しい人生の第一歩を踏み出した---
フィリピン、ミャンマー、タイ 東南アジアのフィールドを巡った体験記
アメリカの大学で応用人類学を学んだ女性が、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の職員になって、フィリピンのベトナム難民キャンプ、ミャンマーからバングラデッシュへ逃れて戻された人々のキャンプ、ミャンマーからタイへ逃れてきた人たちのキャンプでの経験をつづったエッセー。
と、聞くと熱い志と正義感とか、現場で目にする難民たちの悲惨な生活、みたいな重苦しい内容かと身構えますが、実際は、あまり文章を書きなれていない人ががんばって書いた(けれどさほど肩肘張らない)見聞録。
実際は大変だったろうエピソードをさらっと書いているので読みやすく、けれど見聞きしたことがヘビーなのでなかなか面白い。
(ミャンマーからの難民の「ドライ・ベイビー」の話は驚いた。)
おそらく、本当に育ちがよくてボランタリーな人って、街角の募金箱に小銭を入れるのと同じ感覚でまったく気負わずに難民支援に行けちゃうんだろう。
ただ、逆に、そこにあまり深い葛藤がないのか、あるけどそれを言語化することがないのか、本の中にその辺りが出てこないのがやや残念。
また、難民支援活動は終わりがないものなので、このエッセーもヤマとかキリとかといった盛り上がりとかカタルシスとかがないので、そこも物足りない読後感の理由かしら、と思います。
コメントをみる | 

おいしいベランダ。 午前1時のお隣ごはん (富士見L文庫)
2017年6月15日 読書記録第6紀(13.08~)進学を機に一人暮らしを始めた大学生の栗坂まもりは、お隣住まいのスーツの似合うイケメンデザイナー亜潟葉二に憧れていた。ある時ひょんな事からまもりは葉二に危機を救ってもらうのだが、それは憧れとはほど遠い、彼の真の姿を知る始まりで…!?普段着は黒縁眼鏡にジャージ。ベランダは鉢植えとプランターにあふれ、あげくに草をむしって食いながら「会社辞めてきた」って大丈夫このヒト!?ベランダ菜園男子&野菜クッキングで繋がる、園芸ライフラブストーリー、スタート!
拙宅ベランダは半分アジアン、半分ハーブ(というか薬味?)というコンセプトです。
ようするにチャンポンなのですが、それでもおしゃれなレイアウトに憧れはあって、ベランダガーデニングの本などたまに買っては憧れをこじらせ……もとい募らせています。
ひさびさに密林で「ベランダ」をキーワードに検索したら引っかかったのがこの本。ラノベレーベルでベランダ菜園か~、と興味をひかれて、近所の書店へ行ったらたまたま在庫があったので買ってみた次第。
この作者の代表作、東方ウィッチクラフトは恥ずかしながら未読なのですが、それでも聞き覚えはあったので、その点は安心して買いました。
素直で一途な女子大生と、イケメンツンデレとの掛け合いはテンポよく、ラノベ風ではあるけれど引っかからずに読める文体は好印象。
さらに、ベランダの収穫を使った簡単料理は美味しそうで、うっかり自分ちのベランダに野菜の鉢を増やしたい衝動が(笑)。
この本を読んでいて思い出したのが、遠い昔、まだラノベもYAも名前がなくコバルト文庫みたいなの、だったころに読んだコバルト文庫。タイトルも作者も忘れてしまったのですが、女子高生の主人公が長期不在する従兄の家に期間限定仮住まいする話。わくわくドキドキ初めての一人暮らし☆を疑似体験できて、さらに生活のTipsが増えてすでに独立している読者にもうれしい、このタイプの話は定番なのかもしれない。
ラノベらしく、昨年5月の発刊なのにすでに今月3巻が発売予定なので、続きも読みます。
貧乏お嬢さまと王妃の首飾り (コージーブックス)
2017年1月12日 読書記録第6紀(13.08~)公爵令嬢ジョージーは、王室から盗まれた嗅ぎ煙草入れの行方を追って、南仏リヴィエラへと旅立つ。
その途中、ブルートレインの中で出会ったのは、ココ・シャネル!
シャネルたっての要望で、ファッションショーに出ることに。
フランスの危険で魅力的な男たちにもモテモテで、い よいよ女としての魅力が開花!?
と思われた矢先、殺人の容疑で逮捕さ れてしまったジョージーの運命は……。
コメントをみる | 

ネコを載せておけば売れると思いやがって!
2016年12月31日 読書記録第6紀(13.08~) コメント (2)
ネコノミクスだか何だか知らないけれど、相変わらず雑誌のネコ特集やらネコとのコラボ企画号やらが毎月のように出ております。
で、まんまと踊らされた敗北の記録。
■リンネル特別編集 ねこと私。
https://www.amazon.co.jp/dp/4800265630/
■NyAERA (ニャエラ) (AERA増刊)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MYW67B4/
■建築知識1月号:特集「猫のための家づくり」
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M286QC9/
12月31日、いろんな雑誌が特別号を同時に刊行するというイベントがあって、上の2冊はその関連で出ていたもの。
「ねこと私。」は、おしゃれに暮らしている人の家とネコの紹介ですが、私は最近流行りの顔のつぶれた系や足の短い系の、極端に改良が進んだ猫種があまり好きではないし、家の紹介も特に猫との関連は薄めだったかなぁと。
「NyAERA」は読むところが多くてまだ未読。
「建築知識」は、特集といえど70ページもあり非常に読みごたえがありました。建築専門誌ながら、きちんと猫の専門家からも話を聞いており、これまで知らなかった猫の習性なども押さえてあって参考になりました。
で、まんまと踊らされた敗北の記録。
■リンネル特別編集 ねこと私。
https://www.amazon.co.jp/dp/4800265630/
■NyAERA (ニャエラ) (AERA増刊)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MYW67B4/
■建築知識1月号:特集「猫のための家づくり」
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M286QC9/
12月31日、いろんな雑誌が特別号を同時に刊行するというイベントがあって、上の2冊はその関連で出ていたもの。
「ねこと私。」は、おしゃれに暮らしている人の家とネコの紹介ですが、私は最近流行りの顔のつぶれた系や足の短い系の、極端に改良が進んだ猫種があまり好きではないし、家の紹介も特に猫との関連は薄めだったかなぁと。
「NyAERA」は読むところが多くてまだ未読。
「建築知識」は、特集といえど70ページもあり非常に読みごたえがありました。建築専門誌ながら、きちんと猫の専門家からも話を聞いており、これまで知らなかった猫の習性なども押さえてあって参考になりました。
蹄鉄ころんだ【新版】 (創元推理文庫)
2016年12月20日 読書記録第6紀(13.08~)生涯の伴侶を得て、幸せいっぱいのシャンディ教授をあらたな騒動が襲う。夫妻で訪れた金属工芸店で金銀盗難に巻きこまれたのを手始めに、同僚が愛情こめて育てた美しい雌豚は誘拐され、殺人まで起きてしまう。すべては不幸のおまじない――何者かが逆さに打ちつけた馬房の蹄鉄のせいなのか? 年に一度の馬術競技会が目前に迫るなか、教授は捜査に励む。農業大学の町を舞台に、温かな笑いに彩られた傑作ミステリ・シリーズ第2弾。
コメントをみる |